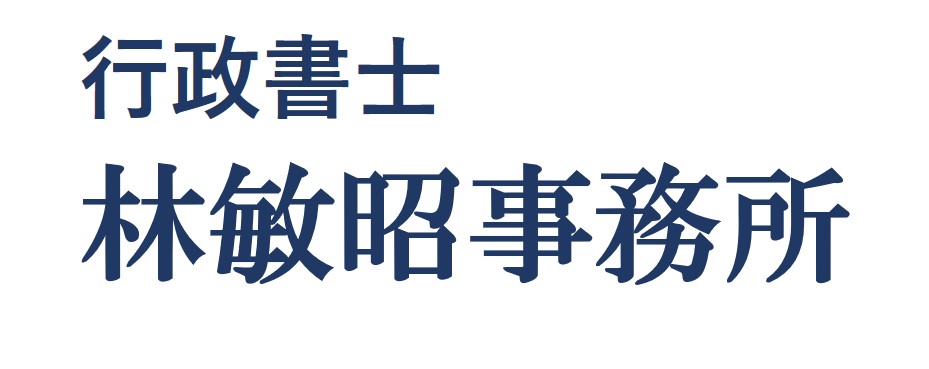遺言
あなたの想いを、確実に未来へ届けるために
こんなお悩みはありませんか?
- 自分の意思をきちんと家族に伝えたい
- 相続トラブルを避けたいが、どうすればよいか不安
- 公正証書遺言の作り方がよくわからない
当事務所のサポート内容
- 遺言書作成に向けたヒアリングと内容整理
- 自筆証書・公正証書遺言の文案作成支援
- 公証人との連携、証人手配
料金の目安
内容や証人手配の有無によって異なりますが、事前に明確な見積をご提示し、納得いただいたうえで着手いたします。
ご相談の流れ
- お問い合わせ(メールまたは電話)
- 面談またはオンライン相談(初回無料)
- 内容の確認・文案作成
- 完成・公証人との調整(公正証書の場合)
対応エリア
岐阜市、関市、美濃加茂市、各務原市など岐阜県全域。オンライン対応で全国からのご相談も可能です。
初回相談無料。お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらお気軽にお問い合わせください。058-374-3439受付時間 平日 9:00-18:00
無料相談はこちら