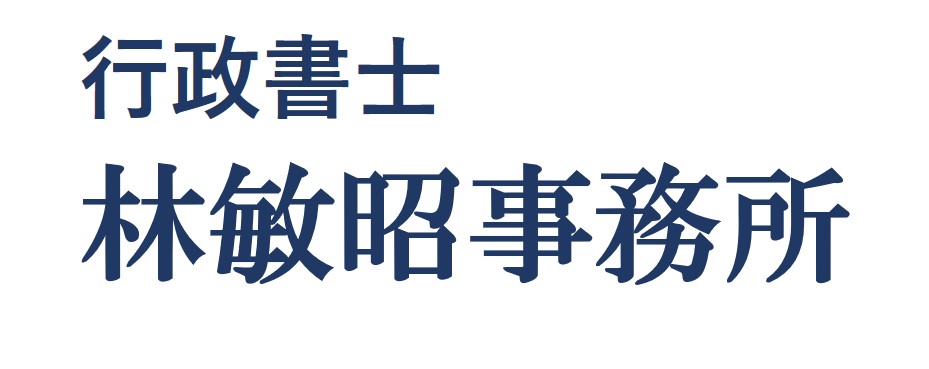1.はじめに――2026年、再び「丙午の年」がやってくる
少し気が早いですが、来年、2026年の干支は「丙午(ひのえうま)」です。
干支は、10年周期の「十干」と12年周期の「十二支」の組み合わせで、60年で一巡します。前回の丙午は1966年、その年、日本ではある社会現象が起きました。
日本では長年にわたり、「丙午の年に生まれた女性は、気性が激しく夫の命を縮める」という迷信が語り継がれてきました。科学的な根拠は全くないにもかかわらず、この迷信が社会に与えた影響は小さくありませんでした。
1966年、前回の丙午の年には、出生数が異常なまでに減少しました。なぜそんなことが起きたのでしょうか。そして、再び丙午の年を迎えるいま、私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。
2.丙午とは?――干支と迷信の関係
丙午は、十干(甲・乙・丙…)の「丙」と、十二支(子・丑・寅…)の「午」が組み合わさった干支です。
「丙」は火の気が強く、「午」もまた火に属するとされることから、「丙午」は“火が重なる年”と考えられてきました。
この火のイメージと関連づけられるように、江戸時代には「八百屋お七」※という少女が放火の罪で処刑された話が語り継がれました。そこから派生し、いつしか「丙午生まれの女性は業が強く、家庭不和や不幸を呼ぶ」という迷信が広まったと言われています。
根拠のない言い伝えですが、時代が進んでもこの迷信は消えず、ついには社会的行動にまで影響を及ぼすことになります。
※八百屋お七が丙午生まれだったという記録はなく、後世の創作によって結び付けられたと考えられています。
3.1966年の“出産控え”――数字に現れた迷信の影響
前回の丙午の年、1966年には日本中で「出産控え」が起きました。
統計によると、1965年に約184万人だった出生数が、1966年には約136万人にまで激減しました。1967年には出生数が約194万人に回復していることから、この減少は、「意図的な出産回避」があったことを明確に示しています。
4.なぜ迷信がここまでの影響を?
1960年代は、日本が高度経済成長の真っただ中にあった時期です。
都市化・近代化が急速に進む一方で、家族制度や結婚観をはじめ、世間体を重んじる伝統的な価値観がまだ色濃く残っていた時代でもありました。
特に「嫁入り」の慣習が残っていた地方では、「丙午の女の子が生まれたら、嫁の貰い手がなくなる」と信じられていたようです。
単なる「迷信」が、社会的圧力となり、実際の出生行動にまで影響を与えてしまったのです。
5.現代はどうか?再び迎える2026年の「丙午」
日本の出生数は、1975年以降はほぼ一貫して下降傾向にありますが、2026年は丙午の影響で、さらに大きな落ち込みが起きることはあるのでしょうか?
時代は大きく変わりました。現代では、多様性を尊重する姿勢が社会通念として定着してきています。
また、いまの若い世代の多くは、「丙午」の迷信そのものを知らないかもしれません。ましてや、「丙午の年に女の子を産むのは良くない」といった考え方は、非科学的で差別的だという認識が、今や社会の常識となっています。
しかし一方で、現代社会にも依然として「同調圧力」が色濃く残っています。「今年はやめておいたほうがいいかもね」という何気ない一言が、若い夫婦の出産の意思決定に思わぬ影響を与えるかもしれません。また、インターネットやSNSの影響で、一部の誤情報や迷信があたかも真実かのように拡散するリスクもあります。
6.おわりに――丙午の迷信から学ぶ、情報と社会のあり方
「迷信を信じるのはバカバカしい」と一笑に付すのも、「念のため避けようかな」と気にするのも、どちらも個人の自由です。
重要なのは、その判断が“自分の意思”に基づいているかどうかではないでしょうか。
1966年に起きた「出産控え」は、個々の信念というより、社会的な同調圧力に押された結果だったのではないかと思っています。
「みんながそう言っているから」といった理由で、本来の判断を曲げてしまう――それこそが問題なのかもしれません。
現代は、SNSやネットによって情報を簡単に発信できる時代です。
発信される情報は玉石混交ですので、フェイクニュースや誤情報、迷信まがいの話に振り回されないように情報を取捨選択する力と、それに基づき自分自身の価値観で判断する力が、ますます求められています。
2026年の丙午は、迷信や噂に流されず、自分自身の価値観と判断基準で行動する大切さを、改めて問い直す機会になるはずです。