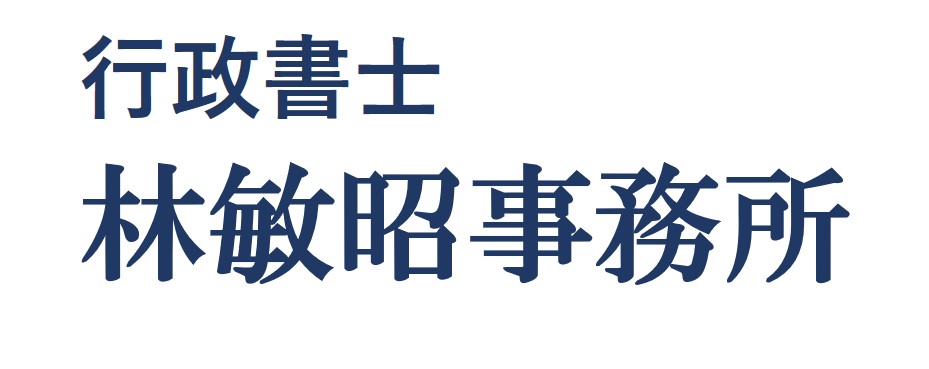フィギュアスケートの本格的なシーズンが開幕しました。
フィギュアスケートといえば、華麗な演技とともに流れる音楽が魅力のひとつですが、近年、音楽使用で著作権が問題となるケースが増えてきました。
そこで今回は、フィギュアスケートにおける音楽使用と著作権の関係について解説します。
1. 著作権が問題となるケースが増えた理由とは?
フィギュアスケート競技では、2014-15シーズンまで、「インストゥルメンタルのみ(器楽曲のみ)」というルールがありました。
このため、選曲は自然と著作権が消滅したクラシック音楽が主流になっていました。
しかし、ルール改正によりボーカル入り音楽の使用が解禁されたことで、映画音楽やJ-POP、洋楽などを使用する選手が急増。
これらの楽曲は多くが現行の著作権保護の対象であり、使用に際しては著作権者や著作権管理団体(例:JASRAC、NexTone)からの許諾が必要となります。
従来はクラシックなどパブリックドメインの曲が多く使われていたため、著作権問題が生じにくかったのですが、ボーカル曲の使用解禁により、現代音楽の利用が拡大し、著作権処理の必要性が高まっているのが現状です。
2. 「編曲権」への配慮も必要
フィギュアスケートの演技時間は、ショートが約2分40秒、フリーが約4分。
このため、原曲をそのまま使用するのではなく、多くのケースで編集(カットや再構成)が行われます。
ここで重要になるのが、「編曲権」です。
著作権法では、著作物に変更を加えるには、原著作者の許可が必要とされています(著作権法第27条)。
つまり、たとえ楽曲を使用する許可があっても、曲の一部を切り貼りして構成を変える場合は別途許諾が必要になるのです。
今後、選手や振付師、コーチに加えて、音楽編集を担当するスタッフも、著作権意識を持った対応が求められるようになってきています。
華やかな演技の裏には、こうした法的な配慮が不可欠になってきているのです。